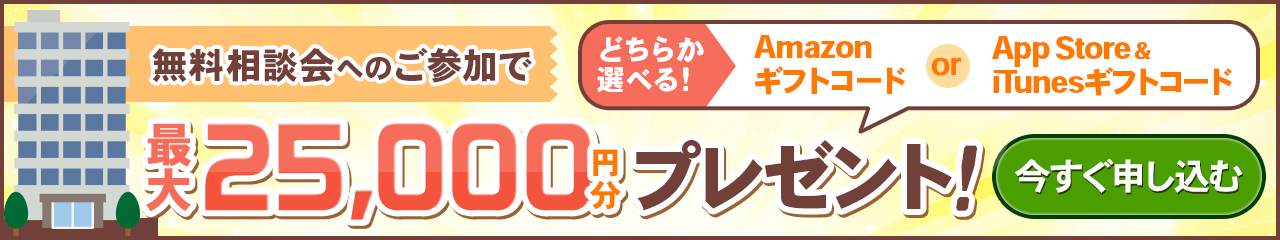お金を貯めるには不動産投資が最適である5つの理由
By Oh!Ya編集部
2,447view
現在の日本の貯蓄状況は、厚労省のデータによると20代の平均額が154.8万円、30代で404万円です。しかし、将来もらえる年金額も不透明な昨今において、子供の養育費を考えるともっと貯金額を増やしたい…という人は多いでしょう。
結論からいうと、お金を貯めるなら不動産投資がおすすめです。今回は、そもそもなぜお金を貯められないか?という点を解説し、不動産投資であればお金を貯めやすい理由を5つ解説していきます。
なぜお金が貯まらないか?
お金を貯めるのは不動産投資が最適である理由を解説する前に、そもそもなぜお金が貯まらないのか?を解説していきます。お金が貯まらない理由は以下3点です。
- 支出を把握していない
- 収入が上がらないから
- 節約には限度があるから
支出を把握していないから
まず、お金が貯まらない理由として挙げられるのは「支出を把握していない」点です。たとえば、月々に支払っている家賃・食費・日用品・交際費…など、正確に把握している人は少ないでしょう。
今は家計簿アプリで簡単に把握できるとはいえ、習慣がないと毎回支出額を入力するのが面倒なのは事実です。しかし、支出を把握しないことには「支出を月々○○円に抑えれば××円貯金できる」という明確な目標が立てられません。
収入が上がらない
お金が貯まらない2つ目の理由は、収入が上がらないという点です。仮に支出を計算していても、毎回決められた支出内に抑えるのは難しいですし、突発的な支出が発生すれば計画は狂います。
そのようなときに、収入が上がっていかない状況だと、少しずつ貯まったお金もすぐに減ってしまい、結果的に「中々お金が貯まらない」という状況になります。
節約には限度がある
単純な話ですが、日々の生活を節約することで、収入が一定でも支出を抑えることができるのでお金は貯まります。たとえば、「毎月の食費と飲み代は4万円以内に抑える」と決めれば、ある程度お金が貯まるでしょう。
しかし、日々の節約には限度があり、仮に今まで月々8万円の食費&飲み代だった人が、いきなり4万円に抑えるのは無理があります。
不可能ではありませんが、生活スタイルがガラッと変わるので、お金が貯まることで「好きなものを食べる楽しみ」や「友達と過ごす時間」など失うものは多いでしょう。
不動産投資でお金を貯めることができる理由
このように、お金がなかなか貯まらない人には前項のような理由があります。不動産投資をすることで前項が解消できる理由は、単純に現在の収入とは別の収入源を確保できるからです。また、不動産投資は節税効果も高いので、節約にもつながります。
もちろん、その収入が不安定であれば意味はありませんが、不動産投資は比較的安定している投資になります。今の収入にプラスして安定した収入があれば、今の生活スタイルを変えない…もしくは過度に節約しなくてもお金は貯まるというわけです。
以下より、不動産投資が安定して収益を得られ、節税効果も高い投資である理由を解説していきます。
理由1:安定している収入源

お金を貯めるには不動産投資が最適である1つ目の理由は、「不動産投資は安定している収入源である」からです。この点について以下を理解していきましょう。
- 不動産投資の基本は家賃収入
- 株価の変動リスクと比較してみる
- 空室や家賃下落リスクは大きくない
安定している収入があることで、支出額が一定であれば自然とお金は貯まっていきます。逆に、収入があっても毎月変動が大きければ、お金を貯めることは難しいです。
不動産投資の基本は家賃収入
不動産投資のメイン収益は家賃収入です。不動産投資の収益の中には、不動産を売却することで得られる売却益もありますが、不動産の売却には諸費用も税金もかかります。そのため、収益を上げる難易度は高いので、売却益はあくまでサブの収入です。
もちろん、空室時は家賃収入がゼロになりますし、築年数が経過するにつれて家賃は下落することもあります。ただし、ほかの投資と比べても家賃収入は安定性が高い投資になるので、「お金を貯める」という意味ではこの安定性は大きな武器になります。
株価の変動リスクと比較してみる
たとえば、株価の変動リスクと家賃収入の変動リスクを比較してみましょう。2014年~2018年の5年間で、日経平均株価の高値と安値を比較すると以下の通りです。
- 最安値:14,096円(2014年5月16日)
- 最高値:24,120円(2018年9月28日)
上記のように、代表的な225銘柄の株価平均値である日経平均株価でも、5年間で約42%もの変動があります。仮に、これを家賃に置き替えてみると10万円の家賃が5年間で5.8万円に下落…もしくは14.2万円に上昇するということです。
何かの事情でこのくらい変動する物件もあるとは思いますが、その可能性は極めて低いといえるでしょう。このように、家賃収入は大きく上昇することも少ないですが、大きく下落することも少ない安定した収入なのです。
空室リスクは大きくない
不動産投資において空室リスクは最大のリスクといえますが、空室リスクは決して大きいものではありません。もちろん、どの物件も空室になる期間はありますが、以下の点でリスクヘッジできます。
- 空室リスクを読み込んでおく
- 空室リスクの小さい物件を選ぶ
- 対策を講じる
空室リスクを読み込んでおく
不動産投資では、長期スパンで収支計算を立てます。その際、空室リスクを読み込んでおくことで、空室時のリスクヘッジが可能です。
たとえば、「1年間で0.5か月空室になる」と読み込んでおけば、仮に空室になっても年間家賃収入にブレはありません。もちろん、想定以上に空室になれば家賃収入はブレますが、それでも空室を読み込んでおくことで、想定よりも大きく収入が減らないようリスクヘッジできます。
空室リスクの小さい物件を選ぶ
そもそもの話ですが、物件を選ぶときに空室リスクが小さい物件を選定することも重要です。たとえば、ターミナル駅が最寄りであったり、住環境に定評があったりする物件です。
もちろん、そのような物件は価格も高いですが、それでも収支計算が合えば「安定して収入を上げられる物件」といえます。
対策を講じる
仮に空室がつづきそうであれば、以下のような対策があります。
- 仲介会社を変更する
- 敷金や礼金を下げる
- 家賃を下げる
たとえば、株式投資をしているときに、株価や配当益が下落しても投資家ができることは「株を売って損切りすること」くらいです。
しかし、不動産投資であれば自分で対策を講じすることができるので、それも収益の安定性につながっています。
理由2:収益性が高い
お金を貯めるには不動産投資が最適である2つ目の理由は、不動産投資は収益性が高いからです。収益性に関しては「利回り」が重要になってくるので、以下を理解しておきましょう。
- 利回りとは?
- 不動産投資の利回り
- そのほかの投資の利回り
- 高利回りはリスクが高い
いくら投資をしても、その投資から得られる収益が小さければ収益額は増えません。不動産投資は利回りが高い上に安定しているので、その点からもお金を貯めやすいのです。
利回りとは?
そもそも利回りとは、簡単にいうと「投資に投下した費用を何年で回収できるか?」という指標です。
たとえば、1,000万円の投資商品を取得し利回り10%であれば、10年間(100%÷10%)で回収できる…つまり年間100万円の収益を上げられるということです。
そのため、投資の利回りはその投資の収益性を測る重要な指標であり、利回りが高いほど収益性の高い投資ということができます。
不動産投資の利回り
不動産投資の利回りには以下3種類あることを理解しましょう。
- 表面利回り:年間家賃収入÷物件価格
- 実質利回り:(年間家賃収入-年間経費)÷物件価格
- 返済後利回り:(年間家賃収入-年間経費-年間ローン返済額)÷物件価格
このように、返済後利回り・実質利回り・表面利回りの順番で精度の高い利回りになります。
広告は表面利回りで表記
前項のように、実質利回りと返済後利回りは、経費とローン返済額を加味して算出します。ただし、この2つの費用は物件によってもローンの借入者(買主)によっても異なります。
つまり、実質利回りと返済後利回りは個別に計算する必要があるので、売り出し物件にこの2つの利回りを表記することはできません。
そのため、最も精度は低いですが、広告には表面利回りが表記されるというわけです。
返済後利回りで2.5~3%ほど
不動産投資をしている個人や法人は、当然ながら自分たちの収益を公表していません。ただ、一般的に都心の物件であれば、表面利回りで10%以上、返済後利回りで2.5%~3%といわれています。
返済後利回りは「手元に残る実際のお金」を元に算出しているので、最も現実的な利回りです。エリアごとの平均利回りは、不動産会社にヒアリングしたり、収益物件サイトでチェックしたりできます。
ほかの投資との比較
さて、前項で解説した「不動産投資の返済後利回り=2.5%~3%」というのは、ほかの投資と比べて本当に高い利回りか?を検証するために、以下の点を解説してきます。
- ほかの投資の利回り
- 不動産投資は融資が利用できる
- 収益額を比較する
ほかの投資の利回り
たとえば、株式投資の利回り(配当金)や長期金利(10年国債など)、REITの利回りは、不動産証券化協会で以下のように公表されています。
- 株式投資(一部上場利回り):2%前後
- REIT:4%前後
- 長期金利:0%前後
このように、マイナス金利政策の影響を受けている長期金利以外は、株式投資と比較してもあまり変わらない…それどころかREITの方が利回りは上です。
上記の利回りは、不動産投資でいう「返済後利回り」のように、実際に手元に残るお金をベースに算出しています。
不動産投資は融資が利用できる
前項のように、不動産投資の利回りは一見高くないように思えますが、実は不動産投資には「融資が利用できる」という大きな強みがあります。
利回りが高いほど手元に残るお金も高くなりますが、「資産額×利回り=手元に残るお金」なので、収益性は利回り以外に資産額も影響してきます。
そして、融資を利用することで資産額を大きくできるので、結果的に不動産投資の収益性は高くなるというわけです。
収益額を比較する
仮に、不動産投資で融資を利用して自己資金の10倍の資産を取得したとします。
株式投資やREITでも、信用取引を利用すると証券会社からお金を借りることができますが、自己資金の3倍程度が限界です。
それらを加味して、仮に400万円の自己資金で投資をしたときの収益額を比較してみましょう。
- 不動産投資:400万円×融資10倍×返済後利回り2.5%=100万円
- 株式投資:400万円×信用取引3倍×2%=24万円
- REIT:400万円×信用取引3倍×4%=48万円
このように、不動産投資は融資を利用できることで収益性が高い投資になります。「理由1」で解説したように、さらに安定性も高いのでお金を貯まりやすいというわけです。
高利回りはリスクが高い
一方、投資の中でも高利回りの商品も存在します。たとえば、マネックス証券の中で「ニッセイアメリカ高配当株ファンド」という商品(投資信託)があります。
この商品は、2019年4月時点の利回りで約17%と高利回りです。ただし、この商品はアメリカの高配当株をメインにおき、そのような株は変動が激しいのが特徴です。
つまり、高利回りで推移する可能性もありますが、大きく下落する可能性もあるということです。
そのため、「ハイリスクでも良いから投資したい」という目的であれば良いと思いますが、「お金を貯める」という目的には沿わないでしょう。
理由3:節税効果が大きい

お金を貯めるには不動産投資が最適である3つの目の理由は、不動産投資は節税効果が大きいからです。不動産投資の節税については以下の点を理解しておきましょう。
- 不動産所得税とは?
- 不動産所得は総合課税
- 減価償却費用の計上
節税することで、支払うべき税金を抑えることができるので支出減につながります。そのため、結果的にお金が貯まりやすくなるというわけです。
不動産所得税とは?
不動産投資の所得(≒利益)は「年間家賃収入-年間経費」で算出され、経費とは以下の項目になります。
- ローン返済の利息部分
- 固定資産税と都市計画税
- 管理委託手数料
- 保険料(火災保険料や地震保険料)
- 管理費と修繕積立金(区分所有)
- 共用部の修繕費用(一棟投資)
- 税理士への報酬(確定申告への依頼時)
- 減価償却費用(詳細は後述)
- その他経費(物件運営のための交通費など)
不動産所得税は総合課税
不動産所得税は総合課税となり、ほかの所得と合算されます。つまり、会社員であれば給与所得と合算し、個人事業主であれば事業所得と合算されます。
つまり、不動産所得が赤字になった場合には、ほかの所得と合算して総所得額が減り所得税も減額されます。
合わせて、所得税額によって税額が変わる「住民税」も節税になる点もメリットといえるでしょう。
減価償却費用の計上
前項で解説したように、不動産所得が赤字になれば所得税・住民税の節税につながります。
しかし、「不動産所得がマイナスであれば、不動産投資によって損失を受けているということでは?」と思う人もいるでしょう。
しかし、上述したように不動産投資の経費には「減価償却費用」が含まれており、この費用が高額になるため節税効果が高いのです。そんな減価償却費用については以下の点を理解しておきましょう。
- 減価償却費用とは?
- 減価償却費用の計算方法
- 減価償却費用を計上できる期間
減価償却費用とは?
減価償却費用とは、物件を取得した金額の建物部分を、毎年「経費」として計上できるお金です。たとえば、毎年100万円の減価償却費用を計上できる物件を購入したとします。
仮に、その年の不動産所得が減価償却費用を除いて40万円であれば、その不動産投資での収益は黒字です。そこに減価償却費用の100万円を経費計上すれば、マイナス60万円になります。
しかし、その100万円はその年に実際に手元から支払っている費用ではなく、ローンを組んで支払っている費用です。
つまり、実際に手元にお金は残っているものの、税務上はマイナス計上できるため節税になっている…ということです。
減価償却費用の計算方法
そんな減価償却費の計算方法は、「建物購入代金×償却率」であり、償却率は構造によって以下のように異なります。
- RC(鉄筋コンクリート造):償却率0.022(耐用年数47年)
- 重量鉄骨:償却率0.030(耐用年数34年)
- 木造:償却率0.046(耐用年数22年)
たとえば、木造の物件で建物価格が2,000万円の場合、減価償却費用は「2,000万円×0.046=92万円」になります。
このように、減価償却費用を高額であり、この費用を計上できる不動産投資は節税効果が高いことが分かります。
減価償却費用を計上できる期間
ただし、減価償却費用を計上できる期間は、築年数と耐用年数によって以下のように異なります。
- 築年数が耐用年数を超えている:法定耐用年数×0.2
- 築年数が耐用年数を超えていない:(法定耐用年数-築年数)+築年数×0.2 ※どちらも端数切捨て
そのため、特に築年数が古い物件は、減価償却費用による節税効果の恩恵を受けられる年数が短いので注意しましょう。
理由4:キャッシュフロー計算がしやすい
お金を貯めるには不動産投資が最適である4つ目の理由は、キャッシュフロー計算がしやすいからです。その理由と、キャッシュフローの作成方法について以下を理解しておきましょう。
- 収入は空室率と家賃下落率を読む
- 経費は突発的な経費を読む
- キャッシュフロー表をつくってみよう
キャッシュフロー計算をしやすいということは、支出額を想定しやすいということです。これは、冒頭の「お金を貯められない理由」で解説した「支出を把握していない」という点を解消できます。
つまり、不動産投資はほかの投資よりも支出が読みやすいという点からも、収入が安定しお金が貯めやすいというわけです。
収入と経費はリスクを読む
まず、収入については空室率と家賃下落率を読み込みます。これら2つのリスクを完璧に読むことはできませんが、不動産会社にヒアリングしながら設定すると良いでしょう。
また、特に家賃下落率については、周辺の物件の賃料を調べてその築年数と家賃を参考に定めることができます。
経費ついては、上述した経費以外にも退去時に発生する共用部の修繕費用や、将来発生する可能性があるリフォーム費用などを読み込みます。
キャッシュフロー表をつくってみよう
仮に、ここでは家賃収入345万円のアパート経営、空室率を年間0.5か月、家賃下落率を年間1%としたキャッシュフロー表をつくってみましょう。
| 年数 | CF | 家賃収入 | 礼金など | ローン支払い | 経費 | 特別経費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 50 | 345 | - | 145 | 80 | 70 | 不動産取得税 |
| 2年目 | 118 | 343 | - | 145 | 80 | - | - |
| 3年目 | 97 | 342 | 30 | 145 | 80 | 50 | 退去時の補修費 |
| 4年目 | 115 | 340 | - | 145 | 80 | - | - |
| 5年目 | 113 | 338 | - | 145 | 80 | 75 | 共用部の補修費 |
| 6年目 | 91 | 336 | 30 | 145 | 80 | 50 | 退去時の補修費 |
| 7年目 | 110 | 335 | - | 145 | 80 | - | - |
| 8年目 | 108 | 333 | - | 145 | 80 | - | - |
| 9年目 | 86 | 331 | 30 | 145 | 80 | 50 | 退去時の補修費 |
| 10年目 | -21 | 329 | - | 145 | 80 | 125 | リフォーム&共用部の補修 |
| 11年目 | 103 | 328 | - | 145 | 80 | - | - |
| 12年目 | 81 | 326 | 30 | 145 | 80 | 50 | 退去時の補修費 |
| 13年目 | 99 | 324 | - | 145 | 80 | - | - |
| 14年目 | 98 | 323 | - | 145 | 80 | - | - |
| 15年目 | 1 | 321 | 30 | 145 | 80 | 125 | 退去時の補修費&共用部の補修 |
もちろん、上記の金額は変わることもあります。しかし、このように不動産投資はある程度収支が読みやすいので、結果的にお金を貯めやすい投資なのです。
理由5:インフレ対策になる

お金を貯めるのは不動産投資が最適である5つ目の理由は、不動産投資はインフレ対策になるからです。その点に関して以下を理解しておきましょう。
- お金の価値は変動する
- 現在の日本はインフレ誘導している
- なぜマイナス金利政策を導入したか?
- 不動産がインフレ対策になる理由
お金の価値は変動する
まず、お金の価値は時代によって変わります。インレフ・デフレという言葉がありますが、インフレとはお金の価値が下がり物価が上がること、デフレとはお金の価値が上がり物価が下がることです。
つまり、お金を貯めていても、そのお金が現金であればインフレ時に目減りしている可能性があるということです。
現在の日本はインフレ誘導している
今の日本はデフレ経済といわれていますが、厳密にいうと物の種類ごとでインフレしているものもあれば、デフレしているものもあります。ただし、現在の日本では、政府方針としてインフレ誘導しています。
つまり、500万円を現金で保有していても、いつの間にかその500万円の価値が下がっている可能性があるということです。
たとえば、現在は500万円で買える車が、インフレにより5年後に550万円になっていれば、相対的にお金の価値が下がっているということです。
不動産がインフレ対策になる理由
では、なぜ不動産がインフレ対策になるかというと、現金と違いインフレになれば不動産価値も一緒に上昇していく可能性が高いからです。具体的には、売却金額と家賃が上昇する可能性が高いです。
たとえば、株式はインフレによって価値が上昇するかは分からず、その企業の業績次第です。しかし、不動産は「モノ」なので、インフレの恩恵を受けやすいといえるでしょう。
せっかくお金を貯めても現金で持っていればインフレ時は目減りしますが、不動産で持つことによってインフレ時に上昇している可能性があります。
まとめ
このように、不動産投資は安定性と収益性が高いという点が、「お金を貯めやすい」という大きな理由になります。
もちろん、投資なのでマイナスになることもありますが、リスクヘッジできる項目が多い点も魅力でしょう。お金を貯めたい…と思っている人は、一度不動産投資について詳しく学んでみてはいかがでしょうか。