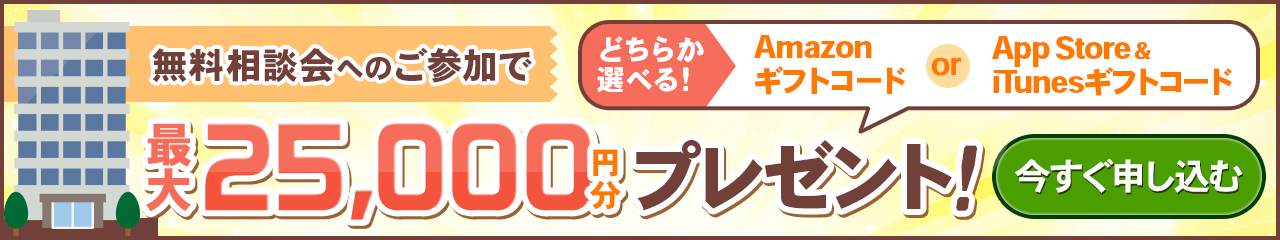【完全ガイド】不動産投資で成功するために取るべき資格5選
By Oh!Ya編集部
1,965view
不動産投資を検討している人の中では、「まずは資格を取ってから…」と思っている人もいると思います。資格を取ってから不動産投資をすることで、不動産投資に関する知識を頭に入れた状態で投資できる点はメリットといえます。
しかし、いざ何の資格を取るべきか?という点は分からない人が多いので、今回は不動産投資で取っておくべき資格5つを紹介するという内容です。この記事を読めば、各資格の概要や難易度、そして不動産投資にどのように活きてくるか分かります。
目次
資格の難易度やおすすめ度
各資格の詳細な解説の前に、今回紹介する5つの資格について、難易度・勉強時間・おすすめ度を一覧表にしました。
| 項目 | 宅建士 | FP | マンション管理士 | 賃貸不動産経営管理士 | 不動産実務検定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ★★★ | 3級★★ 2級★★★ | ★★★★ | ★ | ★ |
| 勉強時間 | 約6か月 | 3級:約3ヵ月 2級:約5ヵ月 | 8か月~1年 | 1~2か月 | 講習のみ |
| おすすめ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
おすすめ度とは、資格が不動産投資に活きる度合いと、勉強時間・難易度を加味した上でのおすすめ度になります。以下より資格ごとの詳細を解説します。
宅地建物取引士(宅建士)

まずは宅建士から解説します。宅建士は不動産関連で最もメジャーな資格であり、不動産会社に勤務している人の多くが取得している資格です。
宅建士とは?
宅建士は国家資格であり、宅地建物取引主任者から改称され「士業」になりました。宅建士の資格を所有していないと、不動産売買時に必要な重要事項説明ができなかったり、売買契約書への署名・捺印ができなかったりします。
そのため、宅建業を営む事務所には「従業員の5名に1名は宅建士の資格を保有している」などの決まりがあるほど、不動産業とは切っても切れない資格です。特に大手不動産会社では宅建士の資格取得を義務化しており、スクールへの通学費用を会社が支払うこともあります。
試験内容と難易度について
宅建士の試験内容は以下の通りです。
- 宅建業法(重説や契約について)
- 民法など(代理や抵当権など)
- 借地借家法や不動産登記法について
- 法令上の制限(建築基準法や農地法など)
- 税金関係(不動産取得税や固定資産税など)
このように、宅建士は不動産に関連する法律や税金など、網羅的に学ぶことができる資格です。また、上述のように難易度は「普通」レベルで、半年程度の学習時間が必要となります。
幅広い法律の知識
宅建士の試験の特徴としては、幅広い法律の知識を求められることです。宅建業法はもちろん、民法や登記法なども絡んでくるため、とにかく量が多いです。ただ、特に民法に関してはほかの資格とも被る項目であるので、汎用性があるといえます。
不動産にまつわる身近なルールや税金
法律以外にも、不動産トラブルにまつわる事例や、不動産の売買に関する税金を学ぶことができます。法律や税金と聞くと堅苦しい印象を持ちますが、いずれも不動産投資と関連が強い部分です。
不動産投資で役立つこと
宅建士は、以下のように不動産投資の全般に役立ちます。
- 物件取得時:登記や重説の内容などの理解
- 仲介会社とのやり取り:仲介手数料のルール
- 税金関係:物件購入時&保有時にかかる税金
- 物件運営時:隣地との境界トラブルなど
宅建士の資格を所有していることで、網羅的に不動産に関する知識・法律・税金が学べるので、上記のように役立つケースは多いでしょう。
難易度は「普通」なものの、ほかの資格と比べると学習時間もかかるため、それを加味しておすすめ度は「★★★」としています
ファイナンシャルプランナー(FP)
次にFPです。FPは一見「不動産」と関わりが薄いように思うかもしれませんが、不動産投資はあくまで「投資」なので、お金のことを学べるFPは役立つ資格です。
FPとは?
FPとはお金全般のプロフェッショナルです。FPのそもそもの役割は、顧客の人生の夢や目標を達成させるために、経済的な意味からプランニングすることです。要は、その人がどんな生活をしたいか?そのためにはどのような収支にする必要があるか?を明確にするのがFPの仕事になります。
不動産会社や保険会社などが「無料FP相談会」などを実施していますが、その際のFPは大体が2級以上のFP資格を保有しています。その人のライフプランをつくらなければいけないので、プランニングの方法から税・保険・相続に関することまで幅広く学ぶことが可能です。
試験内容と難易度について
FPの試験内容は以下の通りです。
- 家計管理(日々の家計管理)
- 老後の生活設計(老後の必要資金)
- 教育資金(教育資金を準備する方法)
- 年金・社会保険(公的年金の仕組みなど)
- 住宅資金(住宅ローンの概要など)
- 資産運用(投資信託や株式投資の概要など)
- 税制(所得税や控除全般について)
- 保険(死亡保障や医療保障)
- 相続・贈与
このように、実に幅広い範囲が出題されます。FP2級は宅建士とほぼ同等の難易度ではありますが、宅建士よりは少々易しい点と網羅できる範囲が広い点で、宅建士よりおすすめ度は高くしています。
不動産投資で役立つこと
不動産投資でFPの資格が役立つときは以下のような時です。
- 今後の収支計算ができる
- ほかの投資との比較ができる
- 将来を考えた設計ができる
今後の収支計算ができる
まずは、FPの本業ともいえる収支計算ができます。ただ、不動産投資でいう家賃収入・物件運営のランニングコストなどを加味した収支計算ではありません。理想の生活を実現させるために、将来的にどのくらいの支出が予定され、どのくらいの収入が必要か?という収支計算になります。
この計算ができれば、不動産投資によってどのくらいの収益を上げる必要があるか?が分かってきて、それに応じて物件価格や利回り、物件種類も分かってきます。
ほかの投資との比較ができる
FPは投資信託や債券、株式投資などほかの投資の概要も学ぶことができます。そのため、ほかの投資と比較した上で不動産投資を選択することが可能です。また、ほかの投資を学ぶことで、不動産投資をしつつ「○○万円は投資信託で運用…」というような結論になるかもしれません。
将来を考えた設計ができる
FPは保険や相続、贈与についても学びます。そのため、保有している資産を生前贈与した方が良いのか…相続税の対策には何をすれば良いか…という点が分かってきます。これは、将来を考えた人生設計ができるということです。
マンション管理士

次にマンション管理士について解説します。マンション管理士も宅建士と同様、不動産関連では比較的メジャーな資格といえます。ただ、宅建士よりも「管理」に特化しているので、一般的とは言い難い資格です。
マンション管理士とは?
マンション管理士とは、その名の通りマンションの管理に関する知識を得られる資格です。マンションは集合住宅なので、入居者全員で管理組合をつくり、管理会社が実際にマンションの運営を任されます。マンションの運営とは具体的に以下のような業務です。
- 長期修繕計画の策定
- 共用の清掃や維持・管理業務
- 管理組合の総会の取りまとめ
- マンション内のトラブルの防止や警告
このように、マンションは一戸建てと異なりマンション内のルールがあり、それを統括するのが管理会社の仕事です。マンション管理士は、そのアドバイザーやコンサルティング的な立ち位置になります。マンションの管理会社の社員や、管理コンサルティング会社の社員が保有している資格です。
試験内容と難易度について
マンション管理士の試験内容は以下の通りです。
- マンション管理に関すること(法令や管理業務)
- 管理組合に関すること(運営の円滑化など)
- マンションの建物や附属施設の構造
- マンション管理の法律に関すること
このように、マンション管理に特化した内容になっています。管理業務を学べるので、特に一棟物件の不動産投資には役立ちます。ただし、資格取得のハードルが高いので、おすすめ度は「★★」です。
不動産投資で役立つこと
不動産投資で役立つことは、やはり集合住宅の管理に関することです。たとえば、区分(一室)マンション投資を検討しており、良い物件が見つかったとします。その際、そのマンションの長期修繕計画や、マンション管理の内容を見ることで、管理会社の質が分かってきます。
「マンションは管理を買え」と言われるくらい管理は資産価値の維持に直結することなので、その点を判断できるのは大きなメリットでしょう。
また、たとえば戸数の少ないアパート経営などは、大半は自分で管理できてしまうこともあるでしょう。そうなると、管理会社へ支払う手数料も安価にできるというメリットにつながります。
賃貸不動産経営管理士
次に賃貸不動産経営管理士について解説していきます。賃貸不動産経営管理士は、その名の通り賃貸不動産の管理に関する資格です。そのため、賃貸物件を運用する不動産投資とは密接な関係があります。
賃貸不動産経営管理士とは?
主に賃貸物件の管理に関する知識を学べる資格です。前項のマンション管理士と似ていますが、マンション管理士よりも易しい資格となります。
マンション管理士は管理会社に勤務している人が、不動産ディベロッパーの社員と対等に話ができるレベルです。賃貸不動産経営管理士は、どちらかというと一般の人に対して賃貸経営をサポートするような資格になります。
資格試験の内容と難易度
賃貸不動産経営管理士の試験内容は以下です。
- 賃貸管理の意義・役割
- 借主の募集に関すること
- 賃貸借契約に関すること
- 管理実務に関すること
- 建物・設備の知識に関すること
- 不動産証券化や税金保険などに関すること
このように、賃貸不動産管理士の試験内容は、賃貸に関することに特化しています。賃貸借契約はもちろん、建物や設備の知識も身に付くので、その点は比較的幅広い資格といえるでしょう。難易度も「易しい」というレベルです。この点も加味しておすすめ度は最も高くしています。
不動産投資で役立つこと
賃貸不動産経営管理士の資格は、主に物件を取得して運用するときに活きてくる資格です。賃貸借契約書は仲介を依頼する不動産会社につくってもらいますが、その契約書の添削や追記の判断などもできるようになります。
また、賃貸物件の建物や設備についても知識も得られるので、設備入れ替えや共用部の管理方法を判断するときにも活きてくるでしょう。
不動産実務検定
 さいごに不動産実務検定について解説します。不動産実務検定は前項までの資格とは毛色が異なり、試験なしの講習のみで取得可能な資格です。
さいごに不動産実務検定について解説します。不動産実務検定は前項までの資格とは毛色が異なり、試験なしの講習のみで取得可能な資格です。
不動産実務検定とは?
不動産の実務検定は、以下のような人を対象につくられた資格です。
- 初めて大家になるので賃貸運営に関する基礎を学びたい
- 現在運営している物件の空室を何とかしたい
- 土地の有効活用方法が分からない
このように、まさに不動産投資の「実務」に即した資格といえます。
試験内容と難易度について
不動産実務検定の試験内容は以下の通りです。
- 賃貸市場について(市場の変化やライフプランニング)
- 不動産関連法規(区分所有法や宅建業法)
- 税務について(青色申告や法人化について)
- ローンについて(融資の種類や金利種類について)
- 管理実務ノウハウ(家賃査定の方法やサブリースなど)
特徴としては、賃貸経営の「実務」に即している点です。たとえば、宅建士の試験でも法律関係や税務については出題されます。しかし、それは賃貸経営だけでなく不動産全般にいえることです。また、講師も賃貸会社の社長やFPなど、実務経験が豊富な人達ばかりです。
さらに、上述したように試験がなく講習だけなので、難易度は前項の賃貸不動産経営管理士よりもさらに易しいといえます。その点を加味しておすすめ度はマックスです。
不動産投資で役立つこと
不動産実務検定を取得すれば、賃貸経営全般に関することを学ぶことが可能です。特に、最近の賃貸市場などは刻一刻と変わってくるので、こういうリアルタイムな講習でしか学ぶことはできません。
また、青色申告の方法や法人化のタイミング、そしてサブリースなどの実際の契約形態など、実践に即したことをプロの講師から学べる点も不動産投資に役立ちます。
実務をしながら資格を取得するという方法もある
このように不動産投資に関連する資格は複数あり、それぞれの資格で学べることは異なります。大事なのは、それぞれの資格の概要、難易度、学習時間を知り、それを加味した上でどのくらい意味のある資格かを考えることです。
また、資格を取ってから不動産投資をする…のではなく、とりあえず不動産投資の物件を探しつつ、資格の勉強をするという方法もあります。
そうすれば、物件取得の過程で疑問点が出てきて、それを調べながら勉強ができるので効率が良いです。その方法も合わせて検討してみてください。
まとめ
不動産投資は専門的な要素も多いので、資格を取ることでムラなく網羅的な知識を得ることが可能です。その上では資格取得と不動産投資の相性は良いといえます。ただ、注意点は資格を取ることが目的になってはいけないということです。
資格取得は、あくまで不動産投資を成功させるための手段に過ぎず、その先には不動産運営の成功がなければ意味がありません。その点を踏まえた上で資格はセレクトしましょう。