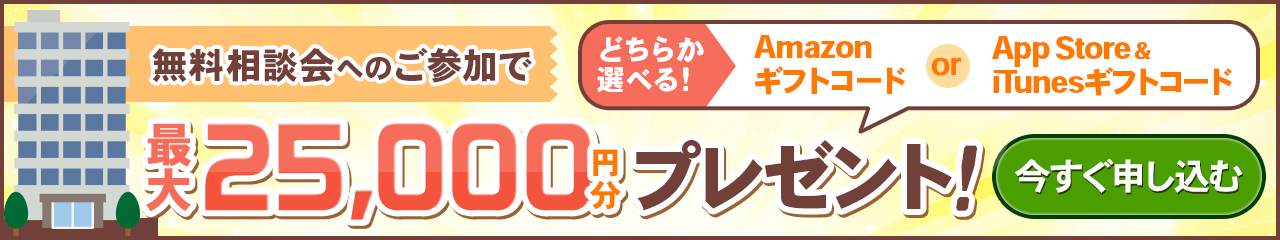【知らないと怖い】不動産投資の連帯保証人について徹底解説!
By Oh!Ya編集部
3,145view
不動産投資を検討している人のほとんどが融資に対する疑問が湧くと思います。その中でも、「自分一人でローンを組めるのか?」という疑問を持つ人は多いのではないでしょうか。今回はそんな人に向けて、連帯保証人を立てて融資を受けるときに知っておくべきことを解説していきます。
不動産を購入するときは妻や夫を連帯保証人にするケースもありますが、そのリスクや注意点を知っておく必要があります。この記事を読むことで、自分の妻や夫を連帯保証人に置くべきかどうかの判断ができるでしょう。
その前に、不動産投資について理解を深めるためには情報収集が大切です。
連帯保証の基礎知識を知ろう
まずは連帯保証人の基礎知識から説明していきます。そもそも連帯保証人とは何かという点を、連帯保証人とよく勘違いされやすい「連帯債務」の違いと共に解説していきます。
連帯保証人とは何か?
連帯保証人とは、主たる債務者(借入者)を保証する人のことで、金融機関のローン審査を有利に進めるためのものとなります。
そもそも、金融機関は融資をするかどうかの判断をするときに、借入者の返済能力の審査をします。その際、借入者に返済能力が足りないと判断されれば融資が下りず、不動産投資ができなくなることもあるでしょう。
妻や夫を連帯保証人にすることで、万が一借入者が返済不能になったときに保証してもらうことができます。そうすれば、金融機関も安心して融資をすることができます。そのため、基本的には連帯保証人も返済能力を有していることが求められます。
勘違いされやすい連帯債務との違い
次は勘違いされがちな連帯債務について解説していきます。ややこしいことに、連帯債務は連帯保証の役割も担っているので、その点を混合しないように気をつけましょう。
2つのローンを組むのが連帯債務
そもそも、連帯保証人は主たる債務者(メインの借入者)を連帯保証人がサポートするようなイメージです。一方、連帯債務は、お互いに別々のローンを組むというイメージです。
たとえば、A銀行で3,000万円の借入を検討しているとします。連帯保証であれば、夫が3,000万円の借入をして、妻が連帯保証人になるというイメージです。
一方、連帯債務の場合は夫が1,500万円、妻が1,500万円のローンを別々に組むことになります。そのため、夫も妻も同じように審査されるので、どちらもある程度収入がないとローンには通りません。それぞれが主たる債務者なので、審査内容は連帯保証人より厳しいといえるでしょう。
お互いの連帯保証人になる
連帯債務の場合はお互いがお互いの連帯保証人になります。詳しくは後述しますが、連帯保証人は借入者が返済不能になったら借金を肩代わりするので、連帯債務の場合はお互いの借金を肩代わりする可能性があるということです。
夫と妻のどちらも収入があれば、借入額がそれぞれ少額になるペアローンの方が審査には通りやすくなります。ただ、結局はお互いが連帯保証人になりますし、手数料も別々に発生するので、大きなメリットがあるとはいえません。
マイホームの場合は住宅ローン控除をお互い受けられるという大きなメリットがありますが、不動産投資ローンにはそのメリットもないのです。そのため、不動産投資ローンにおいては、連帯債務を組むケースはそう多くはないでしょう。
連帯保証人の法律的な効力

連帯保証人の概要、連帯債務との違いが分かったところで、次は連帯保証人とは法的にどのような立場なのかを解説します。連帯保証人は、法律用語でいう以下3つの権利および利益がありません。
- 催告の抗弁権
- 検索の抗弁権
- 分別の利益
この3つがないことで、連帯保証人はリスクを負うことになります。この章では、妻や夫を連帯保証人にして融資を受ける上でのリスクを解説していくので、きちんと理解しておきましょう。
なお、以下でいくつか例を出していますが、そこではA銀行から夫が主たる債務者として借り入れて、妻が連帯保証人になったときを想定しています。
催告の抗弁権
催告の抗弁権とは、保証人(妻)が債務者(夫)にローンの支払いを催促するよう債権者(A銀行)に要求できる権利をいいます。連帯保証人にはこの権利がないのです。
本来は債務者がローンを支払う
本来、A銀行には夫が返済義務を負います。当然ながら、夫の口座から返済額が毎月引き落とされて、仮に滞納すればすぐに夫に連絡がいきます。ただ、数か月しても滞納がつづけば、債権者であるA銀行は保証人である妻に支払いを請求できます。
催告の抗弁権がある・なしの違い
仮に、催告の抗弁権があれば、妻はA銀行に対して「夫に請求してくれ」と主張できるということです。しかし、連帯保証人になってしまうと抗弁権がないので、妻はA銀行に「夫に請求してくれ」と主張できません。
つまり、A銀行が妻に請求した時点で、妻は夫の借金を支払わなければならない義務を負うことです。そうなると、連帯保証人は自動的に主たる債務者の借金を背負うことになります。
検索の抗弁権
検索の抗弁権とは、債務者(夫)に弁済する資力がある場合、保証人(妻)は債務者(夫)が弁済するまで保証債務(肩代わり)を拒否できる権利のことです。連帯保証人にはこの権利がありません。
夫に弁済する能力がある状況とは?
仮に、夫にはお金や資産があるにも関わらず、A銀行からの引き落とし口座だけ残高ゼロになっているとします。そうなれば、A銀行はローン支払いを引き落とせないので、夫は滞納しているという扱いになります。 そうなると、前項のように妻に請求がいくという流れです。
検索の抗弁権がある・なしの違い
仮に、検索の抗弁権があれば、夫に資産があることを主要すれば、妻は支払いを拒否できるのです。しかし、連帯保証人の場合は、たとえ夫に資産があっても請求された以上拒否権はないということになります。
分別の利益
分別の利益とは、保証人が複数名いる場合、頭数で按分した金額のみ保証債務(借金)を負担することをいいます。保証人が複数名いる状況自体、不動産投資ローンではほぼありませんが、一応頭には入れておきましょう。
保証人が複数いるという状況
仮に、主たる債務者である夫の連帯保証人に、妻と父の2人がなるとします。このようなケースは通常の銀行ではほとんど見られませんが、地方銀行や信用金庫などではあり得るかもしれません。金融機関が「1人だと不安だから、2人を連帯保証人にしてくれ」といった場合などです。
分別の利益がある・なしの違い
仮に「分別の利益」があれば、夫が返済不能になったとき妻と父が半分ずつ借金を負います。しかし、連帯保証人はこの分別の利益を受ける権利がありません。そのため、銀行が「返済能力がありそうだから、全額妻に請求する」といっても拒否できないというわけです。
連帯保証人には、これら3つが認められていないので、事実上は借りた本人である債務者と同じ立場といえます。連帯保証人には、それだけ重い責任があるという点を認識しておきましょう。
連帯保証人の審査で注意すべき点

連帯保証人の概要、およびリスクが分かったところで、実際に連帯保証人を立てて審査するときに注意すべき以下を解説していきます。
- 金融機関によって異なる年収換算
- 主たる債務者を誰におくか?の判断
- 基本的には親族しかなれない
- 専業主婦でも連帯保証人を求められることがある
- 保証人を外すことは可能か?
金融機関によって異なる年収換算
上述したように、連帯保証人を立てる目的は、ローン審査に通りやすくするためです。
ローン審査は色々な項目を審査しますが、その中で「年間返済額÷年収」という返済比率も重要な要素です。このパーセンテージが高いと年間返済額が高いと判断され、審査に落ちやすくなってしまいます。
連帯保証人を立てることで、その連帯保証人の年収が借入者の年収にプラスされるので、返済比率が低くなるというメリットがあるのです。ただし、金融機関によってどのくらいの割合をプラスするのかは分かりません。
更に、連帯保証人の年齢や職業、勤続年数などによっても異なるので、正確にいくらが年収としてプラスされるか一概には言えません。これは仲介営業マンの経験でしか分からないので、営業マンと相談しながら、なるべく年収をプラスしてくれる金融機関を選別しましょう。
主たる債務者を誰におくか?の判断
夫婦ともに年収がある場合、どちらを主たる債務者に置くかは重要です。一見、年収の高い方を主たる債務者に置いた方が良いと思いますが、実はそれほど単純でありません。たとえば、以下の経歴だったとします。
- 夫:年収690万円 年齢48歳 契約社員 中小企業勤務 勤続1年
- 妻:年収520万円 年齢37歳 正社員 大企業 勤続15年
この場合は、年齢や勤務形態、勤務先、勤続年数の観点から、妻を主たる債務者にした方が通りやすいかもしれません。この辺りも営業マンの知識次第なところがあるので、良く相談してから決めるようにしましょう。
基本的には親族しかなれない
連帯保証人は基本的に親族しかなれないという点も覚えておきましょう。上述の通り、連帯保証人は主たる債務者と同じくらいの責任を持ちます。言い換えると、金融機関側も主たる債務者をそのように扱っているということです。
そのため、友人や知人などの関係性だと保証人の役割を果たすかどうかは不透明なので、基本的には親族しか連帯保証人になれないと思っておきましょう。
専業主婦でも連帯保証人を求められることがある
専業主婦で金融機関から連帯保証人を求められるケースもあります。繰り返しますが、連帯保証人は主たる債務者と同じような扱いになるので、原則はそれなりの収入がないと連帯保証人にはなれません。
投資物件ならではのルール
ではなぜ専業主婦でも連帯保証人を求めるかというと、物件の相続権利があるからです。つまり、相続した物件からの収益があれば、その収益によって返済ができると判断されるというわけです。この点は、マイホームを購入するときと大きく違う点でしょう。
マイホームの場合は、専業主婦を連帯保証人にはしません。なぜなら、マイホームは家賃収入を生み出すわけではないので、その収益で返済することはできないからです。
専業主婦が連帯保証人になるのは極めて稀
とはいえ、専業主婦が連帯保証人になるのは極めて稀です。というのも、一般的に銀行から借り入れるときは団体信用生命保険(団信)に加入しており、借入者が死亡すれば残債は完済されるからです。
つまり、専業主婦が連帯保証人になるということは、団信をつけていないときでしょう。現在では団信なしで融資をする民間銀行はほぼ皆無なので、専業主婦が連帯保証人になるのは極めて稀なのです。
そのため、この話は昔の話であり、今ではほとんどない話だと思われます。ただ、地方の小規模な金融機関などでは団信無しで展開している可能性はあるので、頭にいれておいて損はないです。
保証人を外すことは可能か?
保証人を立てて借り入れた後に、保証人を外すことは可能ではあります。しかし、その場合は主たる債務者1人で再び審査をして承諾を得る必要があるので、「借り換え」のようなイメージに近いです。
そもそも1人だと審査に通りにくいので連帯保証人を立てるケースがほとんどであり、改めて1人でローン審査に通るハードルは高いといえるでしょう。
連帯保証人を求められるケース

最後にどのようなケースで金融機関から連帯保証人を求められるのかを解説していきます。具体的には以下のようなケースです。
- 返済比率をクリアできない
- 会社の規模が小さい
- 勤続年数が短い
- 融資する物件の収益性・担保価値が低い
返済比率をクリアできない
最も多いのは、上述した返済比率をクリアできていない場合です。金融機関ごとに年収別の返済比率は決まっていることが多く、それに達しない場合はそもそも窓口でNGになるケースがあります。
この点も、担当営業マンと返済比率を計算しながら、連帯保証人を立てるべきか否かを検討することになります。
会社の規模が小さい
勤務先の会社規模が小さい場合も、金融機関の審査は厳しくなります。さらに、契約社員や派遣社員の場合は、今後収入が継続するかが分からないと判断され、さらに審査は厳しくなるでしょう。そのようなときも、連帯保証人を求められます。
勤続年数が短い
前項に付随して、勤続年数が短いケースも金融機関の審査ハードルは上がります。こちらも、継続して安定した収入になるかどうかが不透明であると判断されるからです。
融資する物件の収益性・担保価値が低い
最後は、融資する物件の担保価値が低いときです。不動産投資の場合には、その物件からの収益をローン返済に充てます。そのため、その物件の収益性が低いということは、安定した家賃収入が入ってこずに返済が滞る可能性があります。
また、金融機関は物件に抵当権(担保)を設定するので、最悪の場合にはその物件を売却して返済に充てます。そのため、売却価格が安くなる担保価値の低い物件にも融資を渋るのです。
つまり、その場合は物件ではなく借入者の信用だけが頼りになるので、単体では信用度が低いときに連帯保証人を付けて信用度を上げるというわけです。
まとめ
「連帯保証人」という名称ではありますが、実は主たる債務者に近い責任を負うことが分かったと思います。この点を抑えた上で、連帯保証人になる家族は、どのようなリスクが存在するのかをきちんと説明しなければいけません。
説明して納得してもらった上で連帯保証人を依頼しましょう。また、連帯保証人を立てたからといって、必ずしもローンに通るわけではないので、立てるべきかどうかは営業マンとじっくり相談して決めましょう。
最後に、不動産投資について理解を深めるためには情報収集が大切です。 Oh!Yaの一括資料請求なら、手軽かつ効率的に不動産投資の情報が集められます。