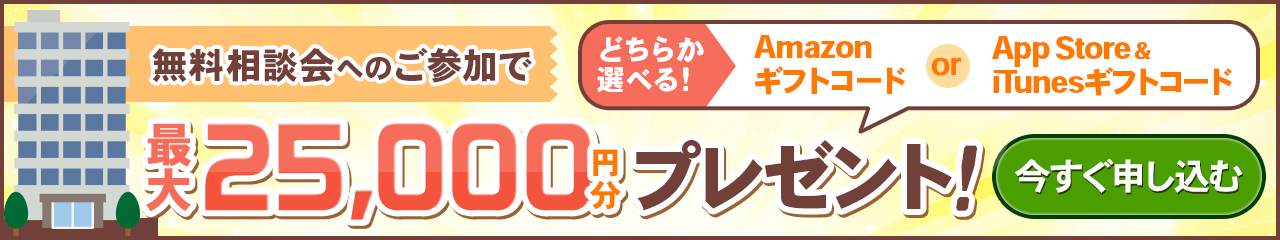不動産投資は法人化すべき?メリット・デメリットと法人化の方法
By Oh!Ya編集部
2,886view
不動産投資をしている人、もしくは検討している人の中では「法人化した方がお得なのか?」と考えている人もいると思います。結論からいうと、ある程度の規模で不動産投資を行っている人は、法人化した方がお得になるケースが多いです。
しかし、まだ小規模投資の場合には法人化を考える必要はありません。ただ、法人化することでメリット・デメリットを理解しておくことは、小規模の不動産投資家の方もプラスになります。今回は、そんな不動産投資の法人化について、メリット・デメリットや法人化する方法について解説していきます。
不動産投資の法人化とは?
「不動産投資の法人化」と聞いても、中々ピンとこない方も多いと思います。そのため、まずは以下の点を理解しましょう。
- 一般的な形態とは?
- 法人化するとは?
- 法人化する方法
- 個人で運営するときとの違い
一般的な形態とは?
一般的に不動産投資をしている人は、サラリーマンであれば「サラリーマン大家」になります。つまり、ある企業に属していながら、副収入として不動産投資をしているということです。これは、法人ではなく「個人で不動産投資をしている」という扱いになります。
または、個人事業主の方が不動産投資をしているのであれば、「個人事業主の事業の1つ」という認定になります。つまり、サラリーマンと同じくあくまで「個人で不動産投資をしている」という扱いです。
法人化するとは?
さて、法人化するとはどのようなことかというと、自分が代表取締役の法人を設立して、所有している不動産の名義を法人にするということです。つまり、今までは個人名であった名義が、「株式会社○○」というような法人名に変わります。法人は個人とは全くの別物なので、税率など根本的に異なるのです。
法人化する方法
ここでは、法人化する方法を簡単に解説します。法人化する流れは以下の通りです。
- 基本事項の決定
- 定款作成
- 資本金の払込み
- 登記書類作成
- 登記申請
- 登記後の各種行政などへの手続き
基本事項の決定
基本事項とは以下のことです。
- 商号(社名)
- 実印の作成
- 資本金額
まずは社名を決め、実印を作成します。そして、その後に資本金額を決めますが、今は株式会社でも資本金1円からスタートできます。
定款作成
定款とは以下を記載することです。
- 事業目的
- 商号
- 本店所在地
- 発起人の名称と住所
- 発行可能株式総数
ここで意識すべきは事業目的です。事業目的は当然「不動産投資」になりますが、将来的に別の事業も行うのであれば一緒に記載しておきましょう。たとえば、株の売買も将来的に行う予定であれば、その旨を記載します。仮に、株の売買を実際に行わなくても問題はありません。
資本金の払込み~登記申請
次に、資本金の振込をして、登記申請書類を作成します。その後、登記申請をして、約2週間後に登記完了です。登記が完了すれば、晴れて株式会社が誕生します。登記に関しての費用は5万円~10万円ほどかかりますが、司法書士に委託する方法が最も楽です。
しかし、登記手続きは司法書士以外も可能なので、ネットなどの情報を参考に自ら行うことも可能です。費用対効果のバランスを見て、司法書士に委託するかどうかを判断しましょう。
合同会社を設立した方がお得?
前項までで解説してきた「法人」は、基本的に株式会社のことです。ただ、実は最近増えてきている会社形態の1つに合同会社というものがあります。結論からいうと、不動産投資の場合は合同会社の設立でも問題ないでしょう。むしろ、初期費用を抑えることができるのでお得といえます。
ここでは、合同会社について以下の点を理解しましょう。
- 合同会社とは何か?
- 株式会社と合同会社の違い
合同会社とは何か?
合同会社は「出資者=会社の経営者」という会社です。つまり、基本的には小規模な会社であり、社長自らに経営権の全てが集中している会社です。この点から、不動産投資を目的とした法人であれば、合同会社で何ら問題ないといえるでしょう。
ちなみに、株式会社は実際に事業を行う「経営者」と、会社の所有者にあたる「出資者(株主)」が分離しています。とはいえ、株主兼代表取締役とすることもできるので、不動産投資の場合は株式会社にしても問題はありません。
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社の違いは以下の点です。
- 登録免許税は合同会社の方が安い
- 合同会社は株式を発行しない
- 合同会社の方が社会的信用は低い
細かい違いはもろもろありますが、知っておくべき違いは上記です。合同会社の歴史は古くないので、その点から社会的信用は株式会社の方が高いといえるでしょう。しかし、後述しますが株式会社の設立費用が20~30万円なのに対して、合同会社は半分以下の費用でできる点はメリットといえます。
個人で運営するときとの違い
後述しますが、法人で不動産投資するときと個人でするときとの大きな違いは、「税金関係」になります。個人の場合は、サラリーマンと同じく個人の所得にかかる所得税が適用されます。個人事業主の場合でもサラリーマンと税率は同じなので、混乱することはないでしょう。
一方、法人の場合は法人が適用される上に、自分はその法人の役員となっています。そのため、不動産投資で稼いだお金を法人の口座から自分の口座に移すときは、法人からの「役員報酬」という形で支払われます。
このように、自分が代表取締役とはいえ、法人は自分とは別人格となるのです。そのため、税金関連のルールが大きく変わり、それがメリットになる場合があります。
法人化のメリット
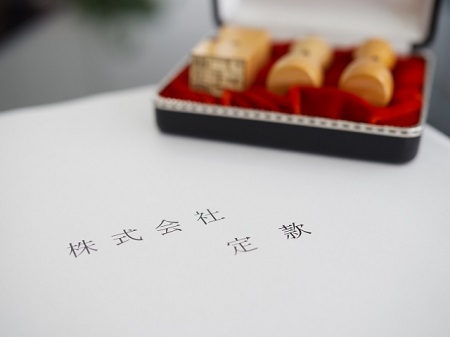
まずは、法人化して不動産投資をするメリットである、以下の点を解説していきます。
- 法人税率が一定になる
- 役員報酬を控除できる
- 所得分散ができる
- 役員への退職金を計上できる
- 費用の計上範囲が広い
- 損益通算の幅が広い
- 連帯保証から離脱できる
- 相続時のメリット
法人税率が一定になる
まず、個人の場合と法人の場合は税率が異なります。個人の場合は所得税が課税され、法人の場合は法人税が課税されるので、それぞれ税率のルールが異なります。その税率の違いによって法人の方が納税額が安ければ、法人化した方が良いといえるでしょう。
所得税の累進課税とは?
個人に課せられる所得税は「累進課税」といい、以下のように所得額に応じて税率が上昇する仕組みです。
| 所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※横スクロールできます。
不動産投資の所得(不動所得)は、給与所得などと合算されます。たとえば、給与所得が年間600万円で不動産所得が100万円であれば、合算して700万円の所得となるのです。上記の計算式に当てはめると、「700万円×23%-636,000円=974,000円」が所得税額になります。
法人税の税率
一方、法人税の税率は資本金が1億円超の法人は約31%、資本金1億円以下の中小法人は22%~34%ほど※です。税率は所得額によって異なりますが、前項の個人に課せられる所得税率ほどの差はありません。
資本金1億円以下の中小企業の最低税率が22%なので、不動産所得と合算した所得額が900万円以上であれば、法人化した方が税率は低くなる可能性があります。この辺りの見極め、税理士と一緒に色々なケースを考えて、法人化するかどうかは検討した方が良いでしょう。
役員報酬を控除できる
次に、法人化すると役員報酬は損金として計上できるので、所得から損金を控除することができ、結果的に所得税の節税につながります。
個人との違いは、以下の「所得の計算式」を見ると分かりやすいでしょう。
- 個人の所得=不動産収入-経費
- 法人の所得=不動産収入-経費-役員報酬
つまり、役員報酬を差し引ける分お得ということです。ただ、役員報酬とは自分個人の所得になるので、個別に所得税がかかります。しかし、その所得は給与所得控除、所得控除、社会保険料を差し引けるので、結果的に法人化した方が節税につながるパターンが多いです。
所得分散ができる
法人化して不動産投資を行うときに、家族を役員にするとします。所有している不動産運営の一部を任せていれば、家族を役員にすることは可能です。
そうすれば、法人所得(不動産所得)は分散されるので、それぞれ控除ができるというわけです。事例として、役員1名の場合と2名の場合で所得額がどうなるか見ていきましょう。前提として、不動産投資をしていて、所得(法人所得および不動産所得)が800万円あるという前提です。
給与所得控除
この事例を紹介する上では、給与所得控除を理解しておく必要があります。給与所得は、勤めている企業(法人)からもらう給与に対して自動的に控除される額で、以下のように給与所得額によって控除率が異なります。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,800,000円以下 | 収入金額×40%※650,000円に満たない場合には650,000円 |
| 180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
| 360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
| 660万円超~1,000万円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
| 1,000万円超 | 2,200,000円(上限) |
※横スクロールできます。
もちろん、自分でつくった法人が得た不動産所得を、全額役員報酬で個人に振り込んだ場合も、それは給与となり給与所得控除は適用可能です。
役員が1名のパターン
このパターンは、自分1名だけが代表となり法人化するパターンです。不動産投資による所得が800万円あれば、それがそのまま役員報酬となります。
その場合の計算式は以下の通りです。 所得額:800万円-200万円(給与所得控除)-38万円(所得控除)=562万円 ちなみに38万円は基礎の所得控除になります。
また、このときの所得税額は以下の通りです。 所得税額:562万円×税率20%-控除額42.75万円=69.65万円
このとき、法人所得(=不動産所得)を全額役員報酬にしているので、法人の所得はゼロとなっています。つまり、法人税はかかりません。
ちなみに、個人で不動産投資をしている場合は、この「給与所得控除」が利用できないので、「800万円-38万円=762万円」に、会社からの給与を合算した所得に税金がかかります。
役員が2名のパターン
一方、役員を2名にして各々の報酬を400万円ずつに設定すると、役員1名の所得額は以下の通りです。 所得額:400万円-134万円(給与所得控除)-38万円(所得控除)=228万円
そして、所得税額は以下の通りです。 228万円×税率10%-控除額9.75万円=13.05万円
つまり、役員2人で26.1万円(13.05万円×2人)の所得税額となるので、役員1人のときの69.65万円よりも大幅に節税できます。そもそも役員1名でも給与控除によって節税効果は大きいので、複数の役員を置くことで、さらに節税できるというわけです。
役員への退職金を計上できる
また、法人化することで役員への退職金を損金として計上することも可能です。もちろん、適正な退職金額である必要はありますが、退職金を損金として計上できれば、さらに所得額を下げられます。
退職金を役員に渡すと、役員は自分もしくは家族なので、「結局個人の所得になり所得税がかかるのでは?」と思う人もいると思います。
しかし、退職金は給与所得以上に有利な計算式、および控除があるので課税所得は極めて低く計上※できるのです。そのため、一時的ではありますが、退職時にはさらに節税効果が高くなります。
ただ、あまりに高すぎる退職金は、税務署から指摘が入る場合があるので、事前に税理士に相談した上で支給することをおすすめします。
費用の計上範囲が広い
また、法人化すれば個人のときよりも費用(経費)の計上範囲が広くなります。たとえば、法人化すれば以下が経費として扱われます。
- 借家の社宅扱い
- 出張手当
- 社員旅行
- 経営セーフティ共済の掛け金
- 生命保険の保険料
ただし、注意点はあくまで「不動産投資に関する費用である」のが前提という点です。そのため、各項目を費用計上するときの注意点を以下より解説します。いずれにしろ、迷ったら税理士に相談した後に、損金として計上しましょう。
借家の社宅扱い
今住んでいる借家を社宅として扱うのは少々難しいです。というのも、自宅兼事務所の場合には全額計上ではなく、せいぜい30%程度の計上が一般的だからです。
さらに、そこで不動産投資に関連する業務を行っている必要があります。また、別途法人用の事務所を借りれば損金計上は全額可能ですが、そもそも事務所の賃料がかかる点を忘れてはいけません。
出張手当
出張手当は、地方の物件を見学しに行ったときの費用などです。これは損金として計上できますが、あまりに高額の場合は税務署から指摘される恐れがあります。
たとえば、年間不動産所得が50万円であるにもかからず、年間の出張手当が80万円であれば、どう考えも不自然です。そのような場合は、税務署の調査が入ってしまう可能性が高いです。
社員旅行
社員旅行の計上は、ある程度大きな会社でないと難しいです。なぜなら、損金として計上できる社員旅行は、あくまで法人を円滑に回すための旅行である必要があるからです。たとえば、自分と妻だけが役員の会社であれば、社員旅行はプライベートな旅行と認定される可能性が高いでしょう。
経営セーフティ共済と生命保険
経営セーフティ共済とは、「取引先の倒産」という不測の事態に直面した法人が、必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度のことです。不動産投資のみを行う法人であれば不要ですが、ほかの事業も行う法人であれば加入する可能性はあります。
生命保険とは、自分も含めた役員が加入する生命保険です。ただ、経営セーフティ共済も生命保険も、支払った分の全額が損金として計上できるかはケースバイケースです。場合によっては、一部だけの損金計上になります。
損益通算の幅が広い
次に、法人化すると損益通算の幅が広いという点です。法人は個人と違い、損益通算の概念が当てはまらず、結果的に個人以上の損益通算が可能になります。これは、家賃収入から得る不動産所得ではなく、不動産を売却したときに得る譲渡所得のことです。
個人と法人の違い
一般的に不動産投資のメイン所得は不動産所得(家賃収入)ですが、将来的に売却して利益を得ることもできます。
そのときに得る利益(譲渡所得)は「分離課税」といい、不動産所得のようにほかの所得と合算できません。しかし、実はこれは個人の話で、法人の場合は事業上の所得となり合算することができるのです。
譲渡所得はマイナスになりやすい
譲渡所得の計算式は以下の通りです。
譲渡所得=(売却価格-売却時にかかった諸費用)―(購入時の不動産価格+購入時にかかった諸費用-減価償却費用)
要は、売却価格から購入金額を単純に差し引くだけでなく、諸費用や減価償却費用を加味するというわけです。とはいえ、土地以外の不動産は経年劣化するので、売却金額は購入金額より安価になっていることが大半です。
つまり、譲渡所得がマイナスになり、法人でほかの事業を行っているとしたら、そのほかの事業の所得から差し引けるというわけです。この点も、法人の方が節税につながるのでメリットといえます。
連帯保証から離脱できる
法人化して融資を受ける際は、大抵は代表取締役である自分自身が連帯保証人になります。つまり、法人名義で融資を受けるものの、返済不能になれば個人である自分自身が返済を迫られるというわけです。
しかし、法人化して実績を積むことで、個人を連帯保証人から外すことも可能になります。つまり、法人が債務不履行や返済不能の状態に陥っても、法人は破綻しますが個人は無傷というわけです。本来は、個人に返済が迫られ、現金がないのであれば資産を取り上げられる可能性もあります。
その点、法人の場合は個人と切り離して考えられるため、個人の資産は守れるというわけです。ただし、一定期間きちんと返済しており、きちんと収益を上げているという実績は必要になります。
お得に生前贈与ができる
法人化して財産を移転することで、低税率で生前贈与が可能です。たとえば、法人をつくり自分を代表取締役、子供を役員にしているとします。その場合、以下のフローによって財産を移転できるのです。
- 個人(自分)が所有している財産を法人に移転する
- その法人から役員報酬として子供に財産を譲渡する
- 子供は評価額を所得として計上する
このように、自分の財産を法人に移し、それを子供に役員報酬として支払うことで、贈与と同じ効果を得られます。また、譲与税や相続税よりも低い税率で譲る渡すことができため、法人化することで贈与税・相続税の節税につながるのです。
ただし、手続きが複雑になり、子供が財産を譲り受けたときに、どの程度の納税額になるかの計算は難しいです。もし、この方法で生前贈与を考えている場合は、一度税理士に相談することをおすすめします。
相続税の節税につながる
個人で所有している収益不動産(賃貸アパートなど)を法人名義にすることで、相続税の節税につながります。少々込み入った話なので、相続の節税に興味がない方は参考程度に読んでおいてください。
まずは、土地と建物のうち、建物を法人名義に移転します。その際、譲渡所得税がかかるので、高額になりそうな土地は移転しません(移転しても良い)。そして、妻や子供を役員にしておけば、その収益不動産から得る家賃収入は、自分ではなく妻や子供が得られるということです
つまり、本来であれば自分が家賃収入を得ますが、その収入は将来的に相続時の財産となり相続税がかかります。しかし、役員報酬として子供や妻に支払うことで、生前贈与と同じ効果を得ることができるというわけです。
もちろん、妻や子供は自分の所得として所得税を支払いますが、上述した通り給与所得控除などもあるので、相続や贈与するよりは安価になるケースがほとんどです。
法人化のデメリット

一方、法人化すると以下のようなデメリットもあります。
- 設立や運営上のコストがかかる
- 赤字でも納税は必須
- 税務調査の対象になりやすい
- サラリーマンが法人化するのは難しい
設立や運営上のコストがかかる
まず、法人設立に伴い、以下のような運営コストが発生、もしくは増額する点がデメリットです。
- 法人の設立費用
- ランニングコストが割高になる
- 事務コストが割高になる
法人の設立費用
法人を設立するときには以下のような費用がかかります。
- 登録免許税
- 実印
- 専門家への報酬
まず、法人として登記するため、20万円~30万円ほどの登録免許税がかかってきます。また、実印は安価でも作れますが、通常は数千円から一万円以上で作成するケースが多いです。さらに、手続きを司法書士などの専門家に依頼した場合、さらに数万円程度の費用がかかってきます。
ランニングコストが割高になる
法人化すると、個人で不動産投資を行うよりも会計処理が複雑になるので、税理士に会計を依頼するケースが多いです。その際、税理士への報酬もランニングコストになりますし、たとえば銀行への振込手数料などの細かい費用が、個人より法人の方が割高になるケースがあります。
事務コストが割高になる
不動産投資用の法人といっても、法人であることには変わりません。そのため、給与支払いや社会保険関係の手続き、労災の手続きなどの事務コストが高くなります。これらを専門家に依頼すると、時間は取られませんが別途報酬がかかってきます。
赤字でも納税は必須
次のデメリットは、赤字でも納税が必須になるという点です。法人の場合は、赤字でも住民税の均等割は発生するので、その税金は納税しなければなりません。
たとえば、東京23区内に事務所を構えており、資本金1000万円以下で従業員が50人以下の法人は住民税の均等割は年額7万円※です。この7万円はどんなに赤字であろうと納税義務があります。
税務調査の対象になりやすい
個人で不動産投資を行うよりも、法人として不動産投資を行う方が税務調査の対象になりやすいです。上述したように法人設立の目的に節税という側面が強いため、その点を税務署が重視してチェックします。繰り返しますが、心配であれば報酬費用はかかるものの、税理士に依頼した方が無難です。
サラリーマンが法人化するのは難しい
結論からいうと、サラリーマンでも問題なく法人化できます。ただし、会社の副業規定に抵触する可能性がある点は気を付けましょう。上述したように、法人化するということは「役員報酬」が発生します。企業からすると、「別法人から収入がある」として、副業として認定される場合があるのです。
個人で行う場合でも不動産所得がありますが、よほど規模が大きくなければ副業として認定されないでしょう。もし、副業として認定されるのであれば、親御さんから相続した不動産は自動的に売却しなければいけないことになるからです。
一方、法人は事業として行っているという認定なので、副業と認定される可能性が高いのです。この点は、一度会社に相談してみることをおすすめします。
まとめ

このように、不動産投資で法人化すると、色々な節税効果が得られます。一番のメリットは、不動産所得をそのまま役員報酬にすることで、給与控除を利用できるので所得税の節税になるという点でしょう。また、役員を増やすことで、その効果は倍増します。
しかし、税金や損金計上のルールが難解であったり、そもそも法人化する手間もかかったりするので、法人化の判断はある程度規模が大きくなったときで良いでしょう。その際は、税理士に交えて、きちんとシミュレーションした後に法人化するかどうかの判断をおすすめします。