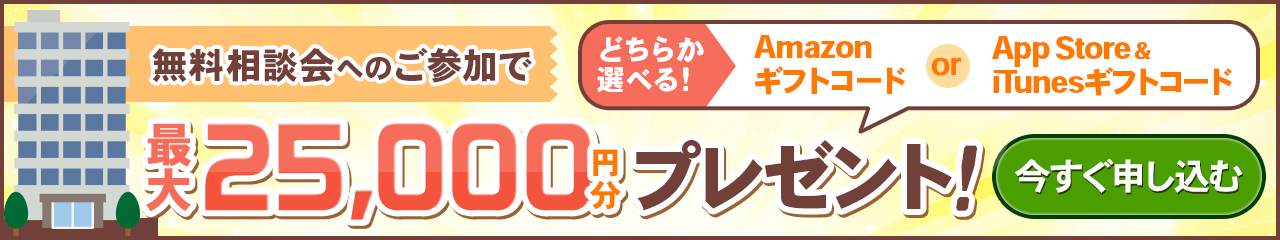【注意喚起】警戒すべき不動産投資の詐欺フレーズ7選!対処法や見極めポイントを伝授
By Oh!Ya編集部
1,655view
悪徳業者による強引なセールス、根拠が無いにもかかわらず成功を約束する商談など、不動産投資の世界には詐欺に等しい行為が絶えません。これらから身を守る第一の術は、まず被害事例を知ることです。
そこで今回は、悪質な売り文句ともいえる「詐欺フレーズ」を紹介し、対処法や見極め方を解説していきます。
警戒すべき不動産投資の詐欺フレーズ7選
不動産売買の成約を急ぐ営業マンの「根拠の無い無責任な情報」を信じたために、大きな損失を被った投資家は数知れず。物件選びが成功を左右する不動産投資において、偽の情報をつかまされることは絶対に回避したいものです。
この項で紹介する誘い文句は安易に信頼せず、購入の理由が明確にならないまま契約を進めないよう注意しましょう。
「すぐに売れますよ」と聞いても即時契約しない

「この物件はすぐに売れる」や「他にも検討中の人がいる」といって焦りを煽る手法は、セールスの常套句。使い古された営業テクニックとして有名ですが、いざ購入検討の段階で使われると心が揺らぐものです。
しかし、モチベーションを刺激された状態で、冷静さを欠いたまま契約に踏み切るのは危険。分析をしないまま売れ残り物件を購入すれば、後悔するだけでなく人生設計そのものが狂ってしまうのです。
初期費用は数百万~数千万円以上と高額であるため、「すぐ売れるから」といった理由で購入に踏み切るのは賢明とはいえません。契約を急かされても熟考する、冷静さと慎重さが大切です。
「高利回りのお宝物件」は賃料のかさ増しに注意
稀に不動産会社や売主が、利回りを高く見せるために物件情報を操作する場合があります。
そのため、不動産会社から送られてくる「レントロール(貸借条件一覧表)」を見るときには、以下のようなポイントを確認しましょう。
- レントロールの作成日
- 賃料相場と検討対象の賃料差額
- かなり以前に契約した入居者の家賃
それぞれ、順番に解説していきます。
注意点1:レントロールの作成日
まず、レントロールの作成日が古くなっているものは注意が必要です。資料の作成日が古いということは、「売れ残り物件で古くなっている」か「現状を知られると都合が悪い」のどちらかに該当すると判断できます。
少なくとも現状の数字をあらわす資料でないのは確実。最新のデータでなければ役に立たないため、新たなレントロールを作成してもらいましょう。
注意点2:賃料相場と検討対象の賃料差額
中古不動産は、部屋ごとに異なる家賃が適用されている場合も多々。このとき、少しでも収益性の見栄えを良くするために、空室の家賃を高めに設定するケースがあります。
そのため、賃料相場とレントロールの現家賃を比較して、現家賃が割高に設定されていないか確認することをおすすめします。
なお、このような情報操作は、次の項で解説する「満室詐欺」と並行して行われがち。スタート段階でのつまずきは後々まで影響するため、与えられた情報を安易に信用せず、自らの手で分析・調査することが重要です。
注意点3:かなり以前に契約した入居者の家賃
契約から長期間経過している入居者の家賃にも要注意。通常は築年数の経過に伴って賃料設定が下落するのですが、入居年数が長い場合は「契約当時の家賃」でそのまま居住しているケースがあります。
もし、この入居者が不動産購入後に抜けてしまえば、契約当時の家賃から「現行の適正家賃」に下方修正しなければならないのです。早々に退去したときの収益性低下を加味して、それでも投資対象に値するのか確認しましょう。
「現状、満室ですよ」は満室詐欺を疑う

1.売主と同性の入居者はいないか
2.管理会社を介さず売主と直接契約している入居者はいないか
3.賃貸借契約書を見たとき、契約日が最近になっている入居者はいないか
これら3つのいずれかに当てはまる場合、満室詐欺の可能性を考慮しましょう。
1と2は親族・知人を利用し、入居偽装を行っている可能性が考えられます。そして、3は「売却に合わせて入居者を用意」したと想定できるため、特に注意を払うべきポイントです。
満室詐欺の疑いが浮上したなら、その入居者たちが購入直後に退去したとき、問題無く運用できるのかを予測。退去が大きな痛手となるなら、営業マンや売主にアプローチして真偽を探るか、その不動産を諦めた方が不用意な失敗を招きません。
投資はときに積極性が求められるものの、わざわざ損失が予想できる場所へ突き進む必要は無いのです。
「節税効果が大きいです」は限られた条件下だけ
「節税効果が大きい」という営業トークを信用して、不動産投資を始めるサラリーマンは多くいます。しかし、不動産投資が大きな節税効果をもたらすのは「不動産収入が赤字」になった場合のみ。
厳密には、不動産収入よりも「運用経費+減価償却費」が上回った場合に限り、本業の給与額を圧縮して節税ができるのです。そのため、利益率が伸び始めたときや償却期間を終えた後は、運用経費が不動産収入を上回ることも無くなり、サラリーマンの給与を節税する効果は失われます。
営業トークでは、不動産購入以降は継続的に節税できるような解説がなされますが、実際には赤字になった場合にのみ発揮される効果だと忘れてはいけません。
なお、不動産の取得年度は「購入経費の集中」で会計上は最も赤字になりやすく、節税効果のピークになることもあります。同程度の節税効果が翌年度に続くことは無いため、初年度と2年目以降は全くの別物であると覚えておきましょう。
「年金代わりになります」は安易に納得しない
賃料収入が年金代わりになることは事実ですが、全ての不動産が利益を生み続けるわけではありません。
- 定期的にメンテナンスされており、住居として魅力がある不動産
- 10年後,20年後も高い賃貸需要が予想されるエリアに位置している
不動産の資産価値は築年数経過に伴い下がるため、対策が無いまま年金代わりとして活用するのは困難。最低でも、上記ポイントは満たしておく必要があります。
営業トークのなかで「年金代わりになります」と勧められた場合は、まず老後時点で期待できる賃料水準から考えてみましょう。このプロセスを面倒に感じて短絡的に決断を下せば、いざ定年退職を迎えたときに、手間と労力だけがかかる収益性の低い不動産が手元に残ります。
「絶対値上がりします」という誘い文句に注意

東京オリンピックや大阪万博など、2020年代は大きな経済効果のあるイベントの開催が決まりました。これにより国内経済に資金が流入して、不動産市場も活発化すると予想されています。
しかし、上記のような訪日外国人の増加は、あくまで不動産市場の「期待要因」に過ぎません。「2020年代は必ず値上がりしますよ」といった誘い文句は、決して確実でないため信用しないよう注意が必要です。
なお、結果が不確実であるのは、株式投資や投資信託も同様。「絶対に稼げる」や「ノーリスクです」といった投資話の多くは、詐欺に等しい悪質な勧誘であると覚えておいてください。
「30年家賃保証します」に潜むサブリース契約の罠
サブリース契約は、保有する不動産を借り上げてもらい、客付けから運用までを一任できる仕組みです。不動産運用の手間が無くなるほか、家賃保証により毎月保証額が受け取れることから、一時期は多くの不動産投資家から注目を集めました。
しかし、初めに設定された保証額は、契約期間のあいだに何度も改定されます。また、魅力として強調される「30年一括借り上げ」は、サブリース会社の意向により変更されるため注意しなければなりません。
これらの問題は下記のような「二重契約」により、不動産投資家の立場が不利になることで起こります。
| 契約の構図 | 法律上の力関係 |
|---|---|
| サブリース会社が入居者に不動産を賃貸 | サブリース会社<入居者 |
| 不動産投資家がサブリース会社に不動産を賃貸 | 不動産投資家<サブリース会社 |
※横スクロールできます。
サブリース会社が不動産の借り手になるため、借地借家法により不動産投資家の立場は不利になります。そのため、サブリース会社の意見には強制力があり、不動産投資家の意見にかかわらず一方的な契約解除も可能。
その反面、不動産投資家の意見が反映されるかは、サブリース会社の裁量次第となっており、解約に伴い違約金を請求されるケースもあります。サブリース契約は決して魅力ばかりでなく、運用が思うように進まなくなる可能性も考慮しましょう。
悪徳業者や詐欺事例の共通点
悪徳業者や詐欺まがいの営業を見抜くことは、決して簡単ではありませんが、おおむね以下に当てはまる場合は「悪質な営業」であると判断できます。
- デメリットを隠したまま商談を進める
- こちらの意思を考慮せず契約を急かす
不動産投資にかかわらず、あらゆる投資はメリットの裏側にデメリットが隠れています。そのため、商談やセミナー時に「デメリットを教えてくれるか」という点は、相手の信用度をはかる目安として機能します。
たとえば、悪質な商談やセミナーでは、デメリットを伝えないまま不動産投資の成約に誘導。強引な営業トークやミスリードを誘う巧妙な話術で、投資家の不安を押しのけて契約を急かすのです。
なお、このような行為は「宅地建物取引業法」に違反しており、営業マンに対して業務停止や免許取消処分が下されます。そのため、悪質な営業行為に遭遇したときには、違反行為だと指摘して商談を終わらせましょう。
しつこくアプローチされる場合には、国土交通省のホームページから「宅地建物取引業免許(知事免許)に関する窓口一覧」に記載されている、各都道府県にある相談窓口への通報も有効です。
「詐欺に騙されない投資家」になろう

悪徳業者が悪いのは事実ですが、偽りの商談を回避するためには投資家側の努力が必要。詐欺フレーズを盲目的に信じることなく、疑い深く熟考する姿勢が求められるのです。
この項では、騙されない投資家になるための「ポイント3つ」をご説明します。
他人の意見を鵜呑みにしない
詐欺の被害事例の多くは、投資家の知識不足や疑いの無さにつけ込んだものです。
たとえ相手が専門家を名乗っていても、投資家目線を追求した提案をくれるとは限りません。1度の成約で大金が動く世界なので、私利私欲のために都合良く話を進める営業マンは少なくないのです。
取引相手の話はアドバイス程度に聞き入れて、大切な選択は自らの意思で決断すべきでしょう。
有名な詐欺事例を把握しておく
仕事や恋愛、料理やゲームなど、あらゆる枠組みのなかでは「ルールや法則を知っている人」ほど優位に立てますよね?これは投資にも当てはまります。
たとえば、ご紹介した7つのフレーズは、どれも珍しい詐欺事例ではありません。事前にこういった被害の存在を知っていれば、簡単に引っかかることは無いのです。
人口減少リスクや災害リスクなど、危険視される不動産投資のリスクはいくつかありますが、最も注意すべきは「無知のリスク」。幸いにも、現代はネットや書籍で手軽に情報が手に入るため、必要なのは学習意欲だけです。
投資詐欺の被害で大切な資産を失わないよう、有名な詐欺事例だけでも調べることをおすすめします。
詳しい知人にアドバイスをもらう
親身になって商談を進めてくれる営業マンがいる一方で、悪質かつ強引なアプローチを繰り返す営業マンもいます。そもそも、契約成立は営業マンのインセンティブに直結するため、全てのアドバイスが「投資家への親切な助言」である方が不自然なのです。
そこで、不動産投資に詳しい知人がいるなら、商談の内容について相談することをおすすめです。無知のリスクは、決して自己学習だけで補完する必要は無く、頼れる人がいるなら積極的にアドバイスをもらいましょう。
数百万円,数千万円の出費だからこそ、全ての「知恵・人脈」を活かすほど成功に貪欲でなければ後悔の原因となります。
まとめ

不動産投資の世界には、今回ご紹介したような詐欺に等しい営業が横行しています。
もちろん、悪徳業者や強引な営業マンは全体の一部ですが、初めて担当に付いた人が良い営業マンだという保証はありません。そのため、基本的に疑いの姿勢を持っていた方が良いのです。
多額の出費を伴う不動産投資において、安易な決断は命取り。今後の人生を大きく変える選択だからこそ、できる限り時間・労力を費やしたうえで購入を検討してみてください。