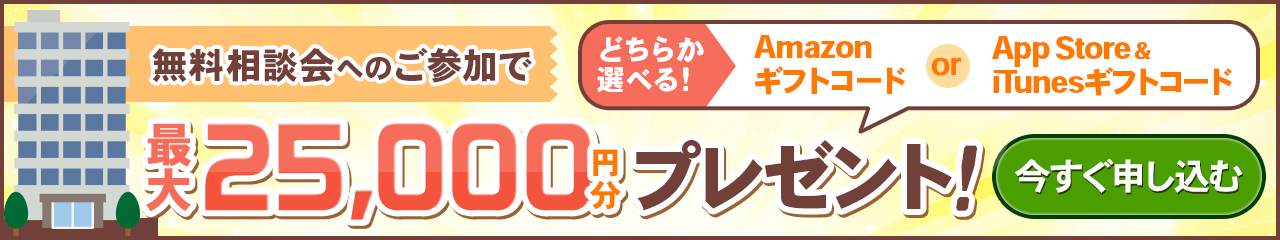不動産投資における「減価償却」とは?具体例を交えて計算を解説
By Oh!Ya編集部
5,911view
不動産投資について調べていると、度々「減価償却」という言葉が登場します。これは多くの人にとって聞き慣れない言葉であり、これまでに教わったことのない概念であるケースがほとんどです。
しかし、不動産投資を続けていくうえで、減価償却への理解は不可欠。10人専門家がいれば、10人が「減価償却を理解すべきだ」というでしょう。
そこで今回は、不動産投資家なら覚えておくべき減価償却の仕組みについて解説していきます。
不動産投資における「減価償却」とは?

減価償却は、物件の購入費用を一定年数に分割して、経費として計上できる会計上の処理です。通常、事業に必要なものを購入した場合は、購入した年の費用として計上されます。
しかし、時間とともに資産性を失う10万円以上の資産「減価償却資産」を購入した場合は、所定の年数に分割されて計上されるのです。不動産も例に漏れず、月日の経過とともに老朽化が進む減価償却資産に分類されるため、購入費用を分割して計算していきます。
減価償却は会計処理にどのような影響をもたらすのか
減価償却では、失われた価値を経費として計上することとなっており、これを「減価償却費」と呼びます。
減価償却費を不動産投資による収入と相殺することによって、税金の計算対象となる課税所得の金額が減り、結果として所得税や住民税は減少。購入年以降も、所定の年数に応じて毎年減価償却費を計上していきます。
こうして、購入費用は一度しか発生していないにもかかわらず、毎年出費として計上して課税所得を圧縮できることから、これを「不動産投資の節税効果」と呼ぶ場合も多いです。
減価償却の計算が必要になる場面
減価償却の計算が必要になる場面は2パターン。不動産投資によって家賃収入を得ている場合、および不動産を物件売却により譲渡所得を得る場合です。
それぞれ、順番に解説していきます。
不動産投資による家賃収入がある場合
一定以上の利益を出している投資家は、確定申告をして納税義務を果たさなければなりません。そのため、物件を人に貸すことで得ている家賃収入から、利益を得るために必要だった経費を差し引いて、納税義務の対象となる課税所得を算出することになるのです。
このとき、課税所得は以下のような計算式で求められます。
| 課税所得を求める計算式 |
|---|
| 課税所得=売上-諸経費(控除なども含む) |
このとき、減価償却も経費に含まれるため、減価償却費がいくらになるのか求めておく必要があるのです。
物件売却により譲渡所得を得る場合
家賃収入は給与と合算される「総合課税」ですが、物件の売却利益は譲渡所得と呼ばれる「分離課税」の対象となっています。この譲渡所得は、以下のような計算式で算出します。
| 譲渡所得を求める計算式 |
|---|
| 譲渡所得=売却価格-(取得費+諸経費)-特別控除 |
上記の計算式のうち「取得費」を実額法や概算法で求めることになっており、実額法を利用する場合には減価償却費の算出が必要となります。
- 実額法:取得にかかった費用の合計額-減価償却費
- 概算法:譲渡収入金額(売却金額)×5%
実額法と概算法で算出した取得費のうち、どちらか大きい値を取得費として使用します。
3ステップ!不動産の減価償却費を算出する方法

減価償却費を算出するためには、いくつかの手順を踏まなければなりません。この項では、減価償却費の計算方法を順番に解説していきます。
ステップ1:償却期間を「建築構造の種類」と「築年数」から求める
まずは償却期間(残存耐用年数)の計算です。償却期間は、建物の「建築構造の種類」と「築年数」によって決まります。
なお、新築物件と中古物件では減価償却の計算方法が違うため、慣れるまでは本記事のような参考資料を見ながら算出することをおすすめします。
新築物件の償却期間は法定耐用年数と同じ
建物が新築物件の場合、償却期間は建物の構造ごとに定められた「法定耐用年数」の年数をそのまま使用します。構造ごとの法定耐用年数は、以下の通りです。
- 木造(W造)22年
- 鉄骨造(S造)19~34年
- 鉄筋コンクリート造(RC造)47年
- 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)47年
建物が頑丈な構造であるほど、耐用年数が長くなる傾向にあります。
中古物件の償却期間は簡便法によって算出する
中古物件の場合は、法定耐用年数と償却期間は同じ値になりません。法定耐用年数は新築の物件にのみ適用される都合上、建物が建てられてから一定の築年数が経過している中古物件は、資産価値の低下を考慮して耐用年数を計算する必要があるのです。
なお、法定耐用年数を完全に終えていない場合と、法定耐用年数を終えている場合とでは計算方法が異なることに留意してください。
法定耐用年数を終えていない場合、中古物件の償却期間は以下の計算式で求められます。
| 法定耐用年数を終えていない場合の計算式 |
|---|
| 償却期間=(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2) |
対して、法定耐用年数を終えている場合は、以下のような計算式を使用します。
| 法定耐用年数を終えている場合の計算式 |
|---|
| 償却期間=法定耐用年数×0.2 |
例として、築20年を迎えた木造物件は、償却期間がどれほどになるのか求めてみましょう。
| 築20年を迎えた木造物件の償却期間 |
|---|
| 償却期間6年=(法定耐用年数22年-経過年数20年)+(経過年数20年×0.2) |
次に、法定耐用年数を終えてしまった木造物件の償却期間を求めます。
| 法定耐用年数を終えている木造物件の償却期間 |
|---|
| 償却期間4年(小数点以下切り捨て)=法定耐用年数22年×0.2 |
このように、築年数が経過するほど新築時に比べて償却期間は短くなります。これは決してデメリットではなく、償却期間が短ければ「購入費用を短期間で減価償却」する都合上、1年ごとの経費が大きくなり課税所得を圧縮することが可能です。
つまり、短期目線では非常に節税効果が高いのです。
ステップ2:不動産を建物(躯体・設備)と土地に分ける

減価償却費を求めるとき、建物部分と土地部分は切り離して考えて、建物部分のみ減価償却費を計算することとなっています。
つまり、土地部分にかかった費用は減価償却の対象になりません。こうして土地が減価償却の対象にならない理由は、土地は「時間の経過に伴って価値を失う」という減価償却資産の基準に当てはまらないからです。
建物部分と土地部分を分けたあとは、必要に応じて建物部分を「躯体」と「設備」に分けます。設備に該当する一例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 給排水設備
- ガス設備
- 衛生設備
躯体と設備は、新築物件であれば売買契約書に記載されていますが、中古物件の場合は記載されていない場合も多いです。
この場合は、躯体も設備も建物部分として計算するのが一般的です。
売買契約書に建物・土地価格が記載されていない場合
売買契約書によっては、建物部分が躯体と設備に分けられていないだけでなく、建物部分と土地部分すら分けられていない場合もあります。こういったケースでは、消費税や固定資産税評価額からそれぞれの値を求めなければなりません。
具体的にどのようにして計算をするか、順番に解説していきます。
売買契約書に記載されている消費税から計算
売買契約書に物件の取得金額と消費税の金額が記載されている場合、消費税から建物部分の費用を算出できます。消費税は土地には課せられず、建物にのみ課せられるからです。
たとえば、平成28年(消費税8%と仮定するため)に取得した物件の取得価格が3,000万円で、消費税の金額が160万円と記載されていたケースで考えてみましょう。
消費税は8%ですので、「160÷8%=2,000万円」といった計算により建物部分の費用が判明し、「3,000万円−2,000万円=1,000万円」と差し引くことで土地にかかった費用を求められます。
売買契約書に消費税が記載されていない場合
売買契約書に消費税が記載されていない場合は、固定資産税評価額を利用して建物と土地の代金を計算可能です。
固定資産税評価額は、固定資産税を計算するとき基準になる価格のこと。建物と土地のそれぞれに評価額が設定されているため、売買代金を建物と土地の固定資産税評価額で按分することで、建物と土地の取得金額を算出することができます。
たとえば、以下のケースにおける建物部分と土地部分の取得金額を計算してみましょう。
- 売買代金総額:6,000万円
- 建物の固定資産税評価額:3,000万円
- 土地の固定資産税評価額:1,500万円
上記の売買代金総額は、建物と土地の合計金額であるため、それぞれの取得金額は分かりません。そこで、売買代金総額を建物の固定資産税評価額である3,000万円と、土地の固定資産税評価額である1,500万円を使用して按分します。
建物の取得金額
6,000万円×(3,000万円/(3,000万円+1,500万円)}
=6,000万円×(3,000万円/4,500万円)
=4,000万円
土地の取得金額
6,000万円×(1,500万円/(3,000万円+1,500万円)}
=6,000万円×(1,500万円/4,500万円)
=2,000万円
このようにして、建物と土地の取得金額を求めることができます。今回の例では建物部分と土地部分の割合を2:1にしたため暗算でも算出できますが、実際はさらに複雑な数値を使うこととなるため上記のような計算式を使って算出すると知っておいて損はありません。
これら一連の計算方法以外にも、建物部分と土地部分の割合は不動産鑑定士への依頼によって算出可能です。ただし、依頼をして鑑定評価書を作成してもらうにあたり、十万円単位で出費が発生するため、費用対効果を見極めて利用することをおすすめします。
ステップ3:償却率をもとに建物部分の減価償却費を求める
建物と土地の取得金額が計算できたら、建物部分の減価償却費を計算します。減価償却費を計算するには、以下の式を利用します。
| 建物部分の減価償却費を求める計算式 |
|---|
| 減価償却費=建物の取得金額×償却率 |
償却率は、建物の法定年数によって決定される数値。具体的な数値は、国税庁の「減価償却資産の償却率表」をご参照ください。
なお、以前は減価償却費を計算する方法として「定額法」と「定率法」という2つの手法が使用されていました。定額法と定率法の違いは、以下の通りです。
- 定額法:毎年一定の金額で減価償却をおこなう方法
- 定率法:未償却部分に償却率をかけて減価償却費を求める方法
定率法は初期の減価償却費が大きくなるため、早期に税負担を軽くする手法として知られていました。ただし、税制改正によって「不動産の取得日」が平成19年の4月1日以降となっている場合は、定額法を用いて減価償却費を計算するように変更されています。
現在、定率法は一定の条件下のみ適用されることとなっているため注意してください。
平成28年3月末までに取得した設備部分のみ「定率法」が利用可能
建物は建物本体と設備に分けることができますが、設備部分においては平成28年3月末までに取得した設備部分に限り、定率法を用いて減価償却費を計算できます。
平成28年4月1日以降に取得した不動産の減価償却費を計算する場合は、定額法を利用しなければならないため、これから不動産投資を始めるなら「原則として定額法を用いる」と覚えておいてください。
ネットや書籍には古い情報が載っているため、この部分に関しては注意が必要です。
不動産の減価償却費を具体例から算出しよう

最後にモデルケースを用いて、減価償却費を実際に算出していきます。新築の木造物件、中古の鉄筋コンクリート造物件などランダムな条件を用意しているので、一緒に計算を追ってみてください。
ケース1:新築木造の物件を購入した場合
新築木造の不動産を2,000万円で購入した場合、減価償却費はどのようになるか計算してみましょう。
| ケース1の条件 | |
|---|---|
| 築年数 | 0年 |
| 建物価格 | 2,000万円 |
| 耐用年数 | 22年 |
| 建物構造 | 木造 |
| 償却率 | 0.046 参考:国税庁「減価償却資産の償却率表」 |
上記の条件であれば、減価償却費は以下のように求められます。
| ケース1の減価償却費 |
|---|
| 減価償却費92万円=建物価格2,000万円×償却率0.046 |
この金額を22年間、減価償却費として毎年経費に計上していきます。
毎年92万円を減価償却していく場合、21年目までは92万円を全額経費に計上できますが、22年目には残高が68万円となるため同額を償却できません。
このとき、最終年度は帳簿上に不動産の存在を残すため、残高が1円となるように償却します。これは「残存価額」と呼ばれるものです。
一連の計算・条件を適用すると、ケース1の場合は22年目に計上する減価償却費が67万9,999円となります。
ケース2:鉄筋コンクリート造のマンションを中古で購入した場合
次に、中古の鉄筋コンクリート造のマンションを中古で4,000万円で購入した場合の減価償却費を計算してみましょう。
| ケース2の条件 | |
|---|---|
| 築年数 | 25年 |
| 建物価格 | 4,000万円 |
| 耐用年数 | 47年 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 償却率 | 0.038 参考:国税庁「減価償却資産の償却率表」 |
中古の不動産の場合は、築年数をもとに耐用年数を計算しなければなりません。新築の場合の法定耐用年数は47年。築年数が25年の場合は、新築の法定耐用年数を超えていないため、以下の計算式を用いて計算します。
| ケース2の償却期間 |
|---|
| 償却期間27年=(法定耐用年数47年-経過年数25年)+(経過年数25年×0.2) |
この計算により償却期間、つまり残存耐用年数は27年だと分かるため、償却率は0.038だと判断できます。
| ケース2の減価償却費 |
|---|
| 減価償却費152万円=建物価格4,000万円×償却率0.038 |
求められた152万円を27年間にわたって減価償却していきます。こちらも先ほどと同様の理由により、購入してから26年目までは152万円を満額償却できますが、最終年度の償却額は47万9,999円となります。
まとめ
不動産を取得すると、減価償却を使って一定額を経費にできますが、不動産の種類や築年数によって計算方法が異なります。計算方法を覚えるのは面倒に感じるかもしれませんが、不動産経営をおこなう際は必須の知識です。
また、減価償却の仕組みを覚えれば、「償却期間が短い中古物件」や「建物部分の比率が高い物件」を選ぶなど、購入前から節税を意識した物件選びができます。今回解説したポイントを参考にして、ぜひ不動産投資に活かしてみてください。